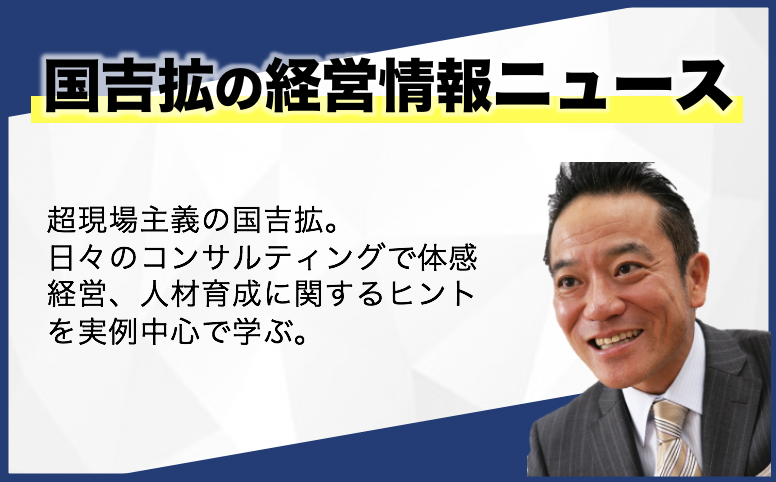◆保険なんか・・・
本コラムでも以前述べましたが、私は新卒で大手保険会社に入社しました。3カ月間の新人研修を経て、配属された部署は東京法人営業部。担当である新宿地区のお客様に経営者保険や団体保険、年金の提案を行う部署です。お世辞にもマジメに営業活動を行っていたわけではありません。外出してもサボり。適当にウソの日報を提出し毎日の業務は終了。成果もでず、成長実感もなく毎日を過ごします。2年目、3年目になっても行動が変わることもなく、結局、3年目の秋に退職に至りました。この3年弱は眠れなくなるほどのストレスに常時苦しみました。
飲み会の席では同期の友人に愚痴文句をよくこぼしていました。「保険なんか、死んだらいくらのギャンブルだろ。こんな商品売りたくないよね」いまでこそ不適切極まりない表現であることは重々理解しています。当時は「ウチの商品は不当に高すぎる」、「わざと難解な仕組みにして消費者をだましている」などと、自社の商品に対し否定的な言葉ばかりあげつらっていました。ただし、本当に「高すぎる」、「難解な仕組み」で「ただのギャンブル商品」を販売する会社であればお客様が商品を購入してくれる理由がありません。たちまち倒産に至っているはずです。時には、「高い」などと意見や文句をいただくこともありますが、大半のお客様は、納得いただいた上で契約します。それを見ながら「なんと無知なのだろう」と不思議に感じていました。
◆営業支援前の現状把握(営業との個別面談)
弊社は売上向上のため、お客様の現場に入り込み会議の運営や指導、研修を行います。営業支援のご相談をいただいた場合、まず、どこに課題があるのか現状を把握するため、様々な角度から分析します。実際の営業現場同行、会議参加、個別面談、など。
ある高級品を扱う会社様の営業支援を行うことになり、全営業と面談を行いました。成績不振者との面談で次のような会話になりました。吉田「自社の商品の特徴は何ですか?」成績不振のAさん「いやー、ウチは競合に比べて高すぎます。社長の方針で絶対に値引きはしませんし。もう少し安ければ売れるんですけどね。」吉田「そうは言っても、利益を残さなければならないですから、値引きはできないと思いますよ。」Aさん「そうですか?価格も高い、質が他に比べて良いわけでもない、これは売れないですよね」確かにこの会社の商品は安いわけではありません。しかし、見事なまでに売れない理由、マイナスの部分をあげていきます。次に毎月目標達成の優秀営業Bさんと面談を行います。吉田「先ほどAさんがウチの会社の価格が高すぎる、と言われていました。そのことについてどう思いますか?」Bさん「確かに他社に比べて高いのは事実です。しかしながら、高額品を購入してくれるお客様は価格よりも別の点に価値を感じてくれますよ。アフターフォローや、丁寧な説明ですとか。」
◆欠点が真っ先に見えてしまう
本能的に、人間は相手の欠点が真っ先に見えてしまいます。視力検査のマークで円の欠けた部分を指示させる理由は、丸く整った部分は気にならないものの、欠けた部分が真っ先に目に入ってくるからです。第一印象も同様。いくら身なりがキチンとしており、笑顔を浮かべていても、言葉づかいが失礼であれば、出来ている部分を帳消しにしてしまいます。これは営業の現場でも同じです。自社の良い部分が多くあるにも関わらず、まず目に入ってくるのはマイナスの部分です。大多数の営業が「あれがダメ」、「これがダメ」と売れない理由のオンパレードです。
◆「売れない理由」ではなく「買ってくれた理由」に着目する
結局のところ、「売れない理由」ばかり述べたところで、売れるわけがありません。営業が取り組まなければならないのは、「なぜお客様が買ってくれたのか、取引を続けているのか」を理解すること。それが「自社の強み」を理解することにつながるからです。そのステップが次の通りです。
①最初に見える欠点にとらわれすぎない
真っ先に見える特長はマイナスです。それにとらわれていれば、売れない理由探しに終始してしまい、売れる理由が見えてきません。
②購入してくれたお客様に決断の理由をたずねる
購入してくれたお客様に商談の最後、「今回はありがとうございます。参考までに決断の一番のポイントは何ですか?」と必ず尋ねるようにしましょう。思いもよらない回答が出てくるはずです。自分では些細なことであっても、お客様にとっては大きなポイントであることも多いです。
③取引を続けてくれている顧客には定期的に顧客満足度調査を行う
取引を続けてくれているお客様には定期的に顧客満足度調査(アンケート)を行い、意見をもらってください。気づかない強みや課題に気づくことができます。
④成功体験の共有
営業同士で朝礼や会議の場で、成功体験を共有することは、営業力強化につながります。営業力とは個人の力と組織の力の掛け算です。ノウハウを独り占めすることなく、共有することが組織全体の偏差値を上げていきます。
⑤「なぜ購入してくれたか」を「自社の強み」として体系化する
成功体験がある程度集まれば、それを「自社の強み」として企画書や商品案内に落とし込みましょう。お客様の心を最も動かすのは事例です。「弊社の取引先であるA社はアフターフォローのスピードを非常に重要視しています。他社では対応できないレスポンスの速さが10年にわたる取引の理由です。」このような文言が新規営業先で響くのです。
【ポイント】
「お客様の購入理由」は自分では気づかない「自社の強み」を教えてくれる。
株式会社経営支援センター チーフコンサルタント 吉田 敬真